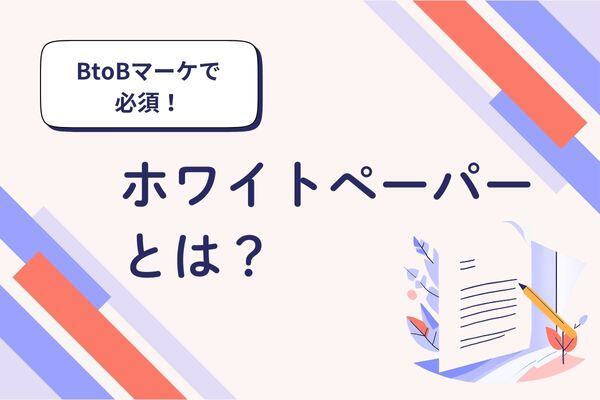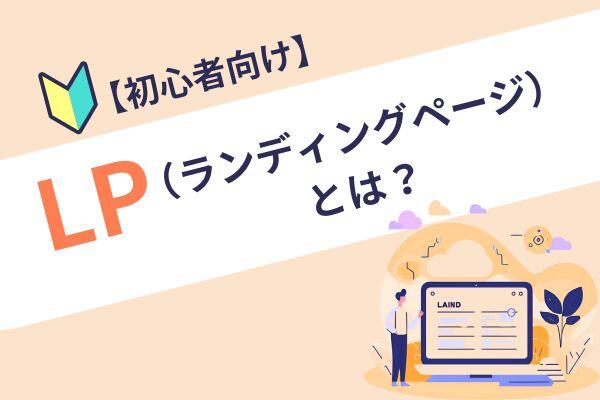
LP(ランディングページ)とは?作成手順から運用時のポイントまで紹介【基礎知識】
Webマーケティング関連の業務を行っていると、よく耳にするLPという言葉。商品・サービスの訴求力が高く、Webマーケティングで成果を出すために欠かせない施策の一つとして、多くの企業で活用されています。しかし、概要は何となく把握していても、役割や作成手順、ホームページとの違いなどを理解できている方は意外と少ないかもしれません。
そこで本記事では、LPの基礎知識をお伝えしたうえで、作成の流れや運用時のコツを紹介します。リードの獲得や売上アップのために、LPの作成をお考えのご担当者様は、ぜひ最後までご覧ください。
2つの意味があるLPとは?
LP(ランディングページ)は、略してLP(エルピー)と呼ばれることもあります。ここでは、LPの概要とその役割、メリットなどを紹介します。
LPの概要
LPには、広義と狭義の2つの意味があります。
広義の意味におけるLPとは、Web広告やSNS、検索エンジンなどを経由して流入してきた訪問者が最初にアクセスするページのことです。訪問者がホームページに着地する(landing)イメージからこの名前がついたとされています。なお、Google Analyticsにおける“ランディングページ”は、広義の意味に該当します。
一方、狭義の意味におけるLPとは、購入や申し込み、問い合わせなどのアクションにつなげるために、商品・サービスの紹介を1枚にまとめた縦長のWebページのことを指します。
このようにLPは広義と狭義で意味合いが異なるため、違いを把握しておきましょう。また、Webマーケティングでもっぱら用いられるのは後者のLPです。そのため、本記事では狭義のLPについて掘り下げていきます。

LPの役割はCV率を最大化させること
LPの役割は、ページにたどり着いたユーザーに購入や申し込み、問い合わせといった具体的なアクションを促すことです。
仮にリンク先をWebサイトのTopページに設定している場合、ほかにも数多くのページがあるので、ユーザーが求めている情報を探せなかったり、ページの遷移自体が手間になることで離脱してしまったりする可能性があります。その点LPであれば、具体的なアクションに直結する情報しか掲載されていないため、離脱が起こりづらくなります。
つまり、LPには離脱を防いで、最終的な成果であるCV(コンバージョン)率を最大化する役割があるのです。
HP(ホームページ)との主な違いはページ数と目的
LPとHPの最大の違いは、LPが1ページで完結し、CVに特化しているのに対して、HPは役割の異なる複数のページで構成されていることです。以下の表に、LPとHPの主な違いをまとめました。
| LP | HP | |
|---|---|---|
| 目的 | CV率を最大化させる | 企業のことを知ってもらう |
| ページ数 | 1ページ | 複数ページ |
| ページの特徴 |
・縦長のデザインで構成されている ・リンクが限定的である ・CTAボタンがある |
Topページから複数のページへとリンクされている |
| ターゲット | 見込み顧客 | 顧客や取引先、従業員、求職者、投資家などのステークホルダー |
| 主な流入経路 |
Web広告やSNS、メルマガ
|
検索エンジン(指名検索、自然検索) |
LPとHPは混同されがちですが、その目的や特徴、流入経路などは大きく異なります。
もし、自社がLPもHPもない創業期の段階であれば、LPよりもHPの制作を優先するとよいでしょう。創業期は顧客や取引先などに企業のことを知ってもらう必要があるためです。HPがあれば、Web上の名刺としてさまざまなユーザーに自社のことを紹介できます。
LPは、あくまでもWebマーケティングの施策の一つです。本格的に集客を検討し始めてから制作しても遅くはありません。なお、創業期であってもLPを作成したい場合は、HPをLPのようなデザインで制作するのも一つの手です。

LP施策が企業にもたらす4つのメリット
LPをWebマーケティングの施策として実施すると、企業は多くのメリットを享受することができます。
- CV率の向上が見込める
- 離脱者が少なくなる
- 必要な情報を理想的な順番で伝えることができる
- 効果計測と改善を行いやすい
何といってもLPは商品・サービスの訴求に特化しているため、ユーザーはページをスクロールするだけで必要な情報を得られます。自ら情報を探し回る必要がないので、CV率の向上につながるというわけです。さらに、LPは他のページへのリンクが限定的であるため、ユーザーが離脱する可能性を減らすことが可能です。
また、LPでは、ユーザーの興味・関心を高めるのに理想的な順番で情報を伝えられることで、CVまでの流れを作りやすいというメリットもあります。1ページで完結しているゆえに、効果計測の手間もかからず、そのぶん改善策も実施しやすいでしょう。
LPの基本構成は3つに分けられる
1ページで構成されているLPは、“ファーストビュー”“ボディー”“クロージング”の3つのパートに分けることができます。これら3つのパートはさらに細かい要素で構成されており、それぞれ役割があります。
| LPのパート | 主な構成要素 |
|---|---|
| ファーストビュー | ・キャッチコピー ・アイキャッチ画像(メインビジュアル) ・CTAボタン |
| ボディー | ・共感コンテンツ ・商品・サービスの情報 ・導入事例 ・利用者の声 ・導入方法 ・CTAボタン |
| クロージング | ・特典紹介 ・よくある質問 ・CTAボタン ・申し込みフォーム |
LPを開いた際に最初に目に入るのが、ファーストビューです。LP内で最も見てほしい情報を、画像やキャッチコピーを組み合わせて伝えましょう。ここでメリットを感じてもらえなかったり、不信感を抱かれたりしてしまうと、ユーザーが離脱する可能性が高くなるため非常に重要です。ページをスクロールして、下部まで読み進めたくなるような工夫を施すことも大切です。
LPの中心となるボディでは、商品・サービスの詳細を記載します。ファーストビューで興味を持ったユーザーにアクションを起こしてもらえるよう、ユーザーの悩みを取り上げて共感したのちに、それを解消できる商品・サービスを説明したり、利用者の声を紹介したりします。文章だけではなく、画像や図も適切に使うとより効果的です。
クロージングは、ユーザーを最終的なアクションへと導く重要な役割を持ちます。商品・サービスの価値を再び強調したうえで、行動を起こすメリットを明示します。また、ユーザーの不安や疑問を解消できるように、よくある質問やサポートサービスなどのコンテンツも盛り込むとよいでしょう。
LPを作成する4ステップ
LPの基本構成を理解できたところで、LPを作成する流れを見ていきましょう。
- 目的・ペルソナを決める
- LPの構成を決定する
- デザインを作成する
- 開発・コーディングを行う
ここからは、代表的なLPの作成手順を紹介していきますので、自社で制作する、または外注する際の参考になさってください。

ステップ①目的・ペルソナを決める
LPを作成する最初のステップは、明確な目的とターゲットとなるペルソナを設定することです。目的を明確にすると、LP全体の方向性を決定し、目指すべき成果を具体化することができます。目的の例としては、新製品の販売促進やメルマガ登録の増加、特定のイベントへの集客などが挙げられます。
また、ペルソナを決めることも同様に重要です。ペルソナとは、ターゲットとする顧客像を具体化したものです。年齢や性別、職業、趣味、生活スタイル、課題やニーズなど、詳細な情報を集めて、理想的な顧客像を描きます。これにより、ターゲットの関心を引きつけて共感を得るLPに仕上げられます。
目的とペルソナは、LPのキャッチコピーを考える際にも重要な訴求軸になるため、ブレが生じないようにこの段階で決めておきましょう。
ステップ②LPの構成を決定する
目的やペルソナを設定したら、LPの構成(ワイヤーフレーム)を決めます。ワイヤーフレームは、7つの領域に分けられます。
- キャッチコピー領域
- 共感部
- サービス提示
- 中間CV
- ベネフィット
- 導入実績
- アクション
これらの要素を網羅すると、訴求力が高いLPの構成を作ることができます。ただし、ワイヤーフレームを決める段階では、すべての要素を詳細に埋める必要はありません。暫定的で構わないので、訴求したい内容を構想してみましょう。
ステップ③デザインを作成する
続けて、LPの効果を左右するデザインを作成します。
設定したペルソナを念頭に置いて、アイキャッチ画像やフォント、文字サイズ、色使いなどを決めていきます。ブランドイメージと一致するフォントや色を選び、視覚的に統一された印象を与えることが重要です。また、CTAボタンは目立つ色で配置し、クリックを促す工夫を施すことも大切です。
なお、自社がアピールしたいイメージや内容だけを積極的に訴求するのではなく、あくまでもペルソナの目線で「魅力的なLPか」「メリット・情報が伝わりやすいか」といった点を検討しましょう。デザインに迷った際は、競合会社のLPを参照して良い点を真似したり、違いを際立たせたりするのも効果的です。
ステップ④開発・コーディングを行う
LPのデザインが確定したら、それをWeb上で機能する形にするためにHTMLやCSS、JavaScriptなどを用いてコーディングを進めます。
まず、デザインファイルを基にしてHTMLでページの骨組みを作成します。この段階では、セマンティックなHTMLを心がけ、SEOにも配慮したタグ付けを行うことが重要です。次に、CSSを用いてデザイン通りのスタイルを適用します。レスポンシブデザインを意識し、さまざまなデバイスでスムーズに閲覧できるようにすることが求められます。JavaScriptは、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにインタラクティブな要素を追加する際に使用します。
また開発段階では、ページの読み込み速度を意識して最適化することも大切です。画像の圧縮やコードのミニファイを行うことで、ユーザーの離脱を防ぎ、検索エンジンからの評価を高めることができます。さらに、開発環境でのテストを繰り返し、あらゆるブラウザとデバイスでの動作確認を行います。これにより、バグや表示の崩れを事前に防ぎ、公開後のトラブルを最小限に抑えることが可能です。これらのコーディングとテストを経て、ユーザーにとって魅力的で機能的なLPが完成するのです。
効果的なLPを作成するための4つのポイント
LPの効果を最大化するには、作成時に押さえておきたいいくつかのポイントがあります。
- ユーザー視点を忘れない
- スマートフォンとPCの両方に対応させる
- EFOを意識する
- 更新しやすい仕様にする
高い成果を上げるためにも、LPの作成時にはこれら4つのポイントを意識してみてください。
ポイント①ユーザー視点を忘れない
効果的なLPを作成するには、ユーザー視点を最優先に考えましょう。ユーザーが探している情報や問題の解決策をいかに迅速かつ明確に提供できるかが、成功の鍵となります。
まず、ユーザーが何を求めているのかを理解し、そのニーズに応じたワイヤーフレームを設計しましょう。これには、ペルソナの設定や利用者へのインタビューの実施が役立ちます。
次に、キャッチコピーや共感部分で関心を引きながら、商品・サービスの利用によってユーザーが得られるベネフィットを説明します。得られるベネフィットを具体的に伝えることで、ユーザーの購買意欲を刺激します。カタログのような物主体のLPになっている場合は、ペルソナ目線の能動的な内容に変えましょう。
ポイント②スマートフォンとPCの両方に対応させる
現在、多くのユーザーがスマートフォンを利用してインターネットを利用しています。そのため、LPを作成する際には、スマートフォンとPCの両方に対応させることも重要です。
レスポンシブデザインを採用することで、デバイスに応じた最適な表示が可能になります。これにより、異なる画面サイズでもコンテンツが正しく表示され、ユーザーエクスペリエンス(UX)を向上させることができます。さらに、モバイルユーザーのためにタップしやすいボタン配置や、読みやすいフォントサイズを選ぶことも大切です。ページの読み込み速度も考慮し、画像や動画の最適化を行うことで離脱率の低減につながります。
また、スマートフォンのユーザーは場所や時間に関わらずアクセスすることが多いため、明確で簡潔なメッセージを伝えることが求められます。これらのポイントを意識することより、ユーザーがすぐに目的の情報にアクセスしやすくなるというわけです。

ポイント③EFOを意識する
EFO(Entry Form Optimization)の意識も、効果的なLPの作成には欠かせません。
EFOとは、フォームの最適化を通じてユーザーの入力をスムーズにし、CV率を向上させる手法のことです。フォームが複雑な場合、ユーザーは途中で離脱してしまうことがあります。これを避けるために、フォームは簡潔で直感的なデザインを心がけましょう。たとえば、入力フィールドの数を最小限に抑えて必須項目を明確にしたり、郵便番号で住所入力をサポートしたりすることで、ユーザーの負担を軽減できます。また、リアルタイムでのエラーチェック機能を追加することで、ユーザーが入力ミスに気づきやすくなり、ストレスを減らせます。
フォームの最適化は、LP全体の成功に直結するため、細部にわたる配慮が求められます。
EFOの基本や実施時の注意点については、以下の記事で詳しく紹介しています。成功事例もまとめておりますので、ぜひご覧ください。
「「LPO」「EFO」それぞれの効果的な活用方法や成功事例を紹介!Webサイトの成功に必要なポイントとは?」
ポイント④更新しやすい仕様にする
LPの効果を持続的に高めるには、更新しやすい仕様にしておくことも心がけましょう。LPは、時代の変化やユーザーのニーズに応じて定期的に更新することが求められるからです。
まず、コンテンツ管理システム(CMS)を活用することで、技術的な知識がなくてもテキストや画像の変更を簡単に行えるようになります。これにより、マーケティング戦略や商品情報の変更に誰でも迅速に対応できます。
また、テンプレートを利用することでデザインの一貫性を保ちながら、更新作業を効率化することも可能です。さらに、定期的な更新はSEO効果にも寄与し、検索エンジンからの評価を高めることにもつながります。
LPの運用を成功させるための3つのコツ
LPは作成すれば終わりというわけではありません。適切に運用することが、CV率の向上につながります。具体的には、以下のコツを押さえたいところです。
- ABテストを実施する
- 分析ツールを利用して、離脱ポイントを把握する
- 適切なタイミングでLPOを行う
費用対効果を最大化するためにも、これら3つのコツを意識してLPを運用しましょう。
コツ①ABテストを実施する
LPの運用を成功させるには、ABテストを実施しましょう。
ABテストは、異なるバージョンのページを同時に公開し、どちらがよりユーザーの反応が良く、高い成果を上げられるのかを比較する手法です。この手法を通じて、訪問者の行動データを基に最も効果的な要素を特定できます。たとえば、ページの見出しやボタンの色、画像の選択といった小さな変更がCVに大きく影響を与えることがあります。
ABテストの実施を通じて体系的に検証し、最適化を図るための客観的なデータを得られれば、費用対効果を高められます。

コツ②分析ツールを利用して、離脱ポイントを把握する
LPの運用を成功に導くためには、訪問者の行動を詳細に把握し、改善点を明確にすることも重要です。なかでも特に注目すべきは、ユーザーがページを離れる“離脱ポイント”です。これを特定するには、Google Analyticsやヒートマップなどの分析ツールを活用することが有効です。これらのツールは、訪問者がどのセクションで興味を失ったのか、または行動を中断したのかを可視化する手助けをしてくれます。
たとえば、ヒートマップ機能を使用すると、ユーザーがどの部分でクリックしたか、スクロールを止めたかが一目でわかります。これにより、コンテンツの配置やボタンの位置、色使いが適切であるかどうかの判断が可能になります。また、訪問者の流れを分析することで、どのパートでユーザーが離脱しているのかを特定しやすくなり、その情報を基にページの改善を図ることができます。
コツ③適切なタイミングでLPOを行う
LPの成功には、適切なタイミングでのLPO(Landing Page Optimization)も不可欠です。
LPOとは、訪問者の行動を分析してページの改善を行うプロセスのことであり、これによってCV率を向上させることができます。ただし、その効果を最大限に引き出すためには、実施するタイミングが重要になってきます。
まず、LPを公開した直後はデータが不十分なため、即座にLPOを行うのは避けるべきです。最初の数週間から数か月間は、訪問者の行動をしっかりとモニタリングし、十分なデータを集めることが大切です。その後、具体的な改善点を見つけるためにデータを分析します。たとえば、訪問者がどのポイントで離脱しているのか、どの要素がクリックされているのかなどの情報を基に、ページの構成やコンテンツを調整します。
また、競合他社の動向や市場の変化に応じて、定期的にLPOを行うことも欠かせません。特に、季節的なイベントや新製品の発売時には、LPの内容を見直しターゲットに適したメッセージを発信することが求められます。このように、データに基づいたタイミングでLPOを実施することで、LPの運用効果を最大化することにつながります。
LPOの基本情報については、以下の記事で詳しく紹介しています。理解を深めたいときにぜひお役立てください。
「【完全版】LPOとは?基本情報と実施フロー&ポイント、ツール選定方法を徹底解説」
LPの参考事例3選

ここまでの説明を受けて、LPの基本情報や作成手順、運用成功のためのコツなどをご理解いただけたのではないでしょうか。そのうえで、参考事例を知っておくと、自社での活用に向けた具体的なイメージを掴むのに役立ちます。
ここでは、LPの参考事例を3つ取り上げますので、参考になさってください。
事例①基本的なレイアウトで作られている宅食のLP
まずご紹介するのは、食品業界大手の企業が展開している宅食のLPの事例です。LPの基本的なレイアウトで構成されているため、作成時にはお手本にしたいものです。
ターゲットが40〜60代と想定されているので、写真のモデルやイラストに同年代を起用することで親近感を演出しています。親しみやすさを目的に明朝体のフォントを使用し、読みやすさと品の良さを兼ね備えているのも特徴です。
また、メインカラーには料理の見栄えを良くする暖色系を採用し、暖かく安心できる印象も与えています。ターゲットに合わせたデザインや雰囲気をLPに反映できている参考事例だと言えるでしょう。
事例②シンプルなデザインで見やすさを重視しているカーリースのLP
続いてお伝えするのは、シンプルさを追求したカーリースのLPです。白を基調に緑をメインカラーとすることで、安心感や安全性を強調でき、サービスに対する信頼感を高めています。自動車のような高額商品、かつ事故の心配がある場合に、安心安全をイメージさせる緑色は相性が良いでしょう。
また、このLPでは最低限の説明に留めているのも特徴的です。なぜなら、カーリースのように契約内容が複雑になる場合、LPですべてを説明しようとするとかえって難解になり、ユーザーが離脱する可能性があるからです。まずは興味を持ってもらうことを優先したうえで、問い合わせや公式サイトへの訪問を促す設計もされているため、CV率の向上が見込めます。
事例③BtoBを想定した勤怠管理システムのLP
最後にご紹介するのは、昨今の働き方の変化に対応したAIによる勤怠管理システムのLPです。BtoB向けであるため事前に調べられることを想定して、オフィスや生産現場、病院など業態別にページを設けたり、FAQ項目を多めにしたりして、比較検討しやすい構成になっています。
ケース別にいくつかの動画が埋め込まれているのも魅力的です。ターゲットの行動パターンを予測して、必要な項目を盛り込んでいるのも参考になるでしょう。
LPを成功させるには、LPOやEFOの実施が重要!
本記事では、LPを取り上げ、基礎知識や作成手順、運用時のコツなどを詳しく紹介しました。
LPの作成時にはユーザー視点を最優先に考え、スマートフォンへの対応やEFOの実施を行うことで、より効果を高めることができます。CV率の向上のために、ABテストや適切なタイミングでのLPOも行いたいところです。
自社だけでLPを作成することも可能ですが、上記のように決めるべき項目や押さえたいポイントが多くあるのもまた事実です。社内の人的リソースが不足している場合は、マーケティング業務を一括代行できるcontennaにお問い合わせください。専門の制作チームが、戦略設計からLP制作、運用改善まで貴社のマーケティング活動をまるっとサポートいたします。ご相談は無料ですので、ぜひ一度ご相談ください!

.jpeg)